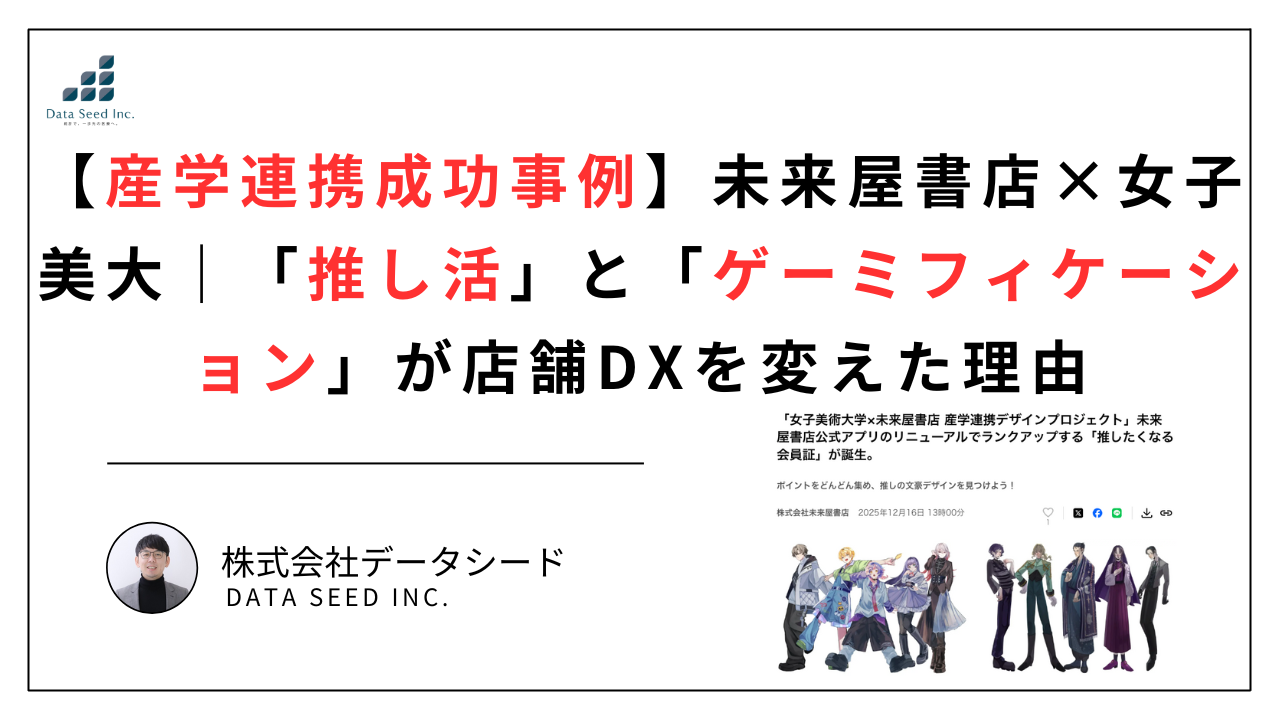「産学連携」という言葉を聞いたとき、多くのビジネスパーソンはどのような光景を思い浮かべるでしょうか。 理系の研究室における新素材開発や、工学部とのロボット共同研究などをイメージする方が多いかもしれません。
しかし、今、文系・芸術系の大学との連携が、企業のマーケティングやブランディングに革命を起こしつつあります。
今回は、イオングループの書籍専門店「未来屋書店」と「女子美術大学」による産学連携プロジェクトを徹底解説します。
単なる「学生によるデザインコンペ」の枠を超え、「ゲーミフィケーション(ゲーム要素の活用)」や現代の「推し活文化」をビジネスに実装し、公式アプリのリニューアルを成功させた事例です。
なぜ、大人の会議からは生まれなかったアイデアが、学生との連携によって実現できたのか。Amazon全盛の時代に、リアル店舗が提供すべき「情緒的価値」とは何か。その本質に迫ります。
(※本事例は他社様の取り組みを紹介するものであり、弊社の実績ではありません。素晴らしい取り組みのため、業界の動向としてご紹介させていただきます。)
産学連携プロジェクトの背景:店舗アプリは「作業」になっていないか?
プロジェクトの舞台は、全国に店舗を展開する「未来屋書店」の公式スマートフォンアプリのリニューアルです。
多くの小売店がアプリを導入していますが、その多くは「ポイントカードのデジタル版」に留まっています。
レジでスマホを取り出し、アプリを立ち上げ、バーコードを表示する。これはユーザーにとって、ポイントをもらうための「事務的な作業」であり、「面倒くさい」と感じる瞬間でもあります。
「どうすれば、ユーザーが自ら進んでアプリを開きたくなるのか?」 「どうすれば、来店すること自体が楽しみになるのか?」
この課題に対し、未来屋書店がパートナーに選んだのが、女子美術大学の学生たちでした。 そして生まれたコンセプトが、**「推したくなる会員証」**です。
産学連携成功の鍵1:本を買う行為を「育成ゲーム」に変える

このプロジェクトの最大の特徴は、アプリの中に明確な「ゲーミフィケーション」を取り入れたことです。
「たまごっち」世代のDNAを刺激する
音声解説でも触れられていますが、このアプリの仕組みは、かつて社会現象となった「たまごっち」や「デジモン」などの育成ゲームの構造によく似ています。
従来のアプリでは、「本を買う=ポイントが貯まる」という等価交換が行われるだけでした。 しかし、リニューアル後のアプリでは、このプロセスが以下のように再定義されました。
- 本を買う = キャラクターにご飯(エサ)をあげる
- 来店する・購入する = キャラクターが成長・進化する
このように意味づけを変えることで、ユーザーの行動原理が変わります。 「ポイントが欲しいからアプリを出す」という受動的な動機から、「キャラクターを育てたいから本を買う」「進化を見たいからお店に行く」という能動的な動機へと変化するのです。
自分の手塩にかけた対象が変化・成長していく様子を見守りたいという欲求は、人間の本能的なものです。この心理を巧みに突き、面倒な「会計時の作業」を「エンターテインメント」へと昇華させました。
産学連携成功の鍵2:企業論理を打破する「学生のインサイト」
このプロジェクトが産学連携である必要性は、キャラクターの設定と世界観の構築に強く表れています。
「万人受け」を捨てる勇気
もし、企業の担当者だけでキャラクターを作ろうとしたら、どうなっていたでしょうか。 おそらく、「老若男女に嫌われない、無難で可愛い動物のキャラクター(マスコット)」が採用されていた可能性が高いでしょう。これは企業としてのリスク管理や、最大公約数を狙うマーケティングとしては正解ですが、ユーザーの「熱狂」を生むことはありません。
しかし、女子美大の学生たちが提案し、採用されたのは以下のようなキャラクターたちでした。
- カフカ
- シェイクスピア
- 太宰治
実在の「文豪」をモチーフにした、非常に物語性の強いキャラクターです。 しかも、ただのマスコットではありません。アプリの会員ランク(ブロンズ、ゴールド、プラチナなど)が上がるにつれて、キャラクターの衣装が豪華になり、物語が進展していくという詳細な設定が組み込まれています。
「推し活」文化の実装
ここには、現代の若者特有の「推し活」の感性が反映されています。
今の大学生世代にとって、「推し(好きな対象)」を応援し、その成長を見守ることは日常の一部です。
「カフカの世界観を衣装に反映させたい」「ランクが上がると物語がどう動くのか見たい」――こうした、ある種マニアックとも言える「濃いストーリー性」こそが、今の消費者の心を動かすことを学生たちは肌感覚で知っていました。
大人の社員が会議室でどれだけ議論しても、「カフカを育成キャラにしよう」という発想には至らなかったでしょう。 企業の論理では「リスク」や「ニッチすぎる」と切り捨てられそうなアイデアを、「今の時代はこれが刺さるんです」と提案できる。これこそが、Z世代の学生と連携する最大のメリットです。
本産学連携に関してビジネス視点の分析:機能的価値から「情緒的価値」への転換

この事例をビジネス的なフレームワークで分析すると、「機能的価値」から「情緒的価値」への転換という成功要因が見えてきます。
Amazonに勝てない「機能」の戦い
書籍販売において、リアル店舗は非常に厳しい戦いを強いられています。 「本を買う」という機能だけを見れば、AmazonなどのECサイトのほうが圧倒的に便利です。品揃えは無限に近く、家まで届けてくれて、価格は再販制度によりどこで買っても同じです。
つまり、「利便性(機能的価値)」だけで勝負している限り、リアル書店がECサイトに勝つことは困難です。 ユーザーに「わざわざ店に足を運ぶ理由」を提供しなければなりません。
「わざわざ行きたい」を作る情緒的価値
未来屋書店のアプリは、ここに「情緒的価値(感情に訴えかける価値)」を付加しました。
- 機能的価値: 本が手に入る。ポイントによる値引きがある。
- 情緒的価値: 「推しのキャラが進化した!」「育成が楽しい!」というワクワク感。
「本を買う」という結果だけでなく、「本を買ってキャラを育てる」というプロセスそのものに価値を持たせたのです。 この「プロセスを楽しむ」「体験を楽しむ」という要素は、Amazonのワンクリック購入では決して得られないものです。
これは「パンを買うためにパン屋に行くのではなく、あの店員さんに会いたいからパン屋に行く」という心理に似ています。 商品そのものの差別化が難しい時代だからこそ、商品に付随する「物語」や「体験」で差別化を図る。このアプリは、まさにその戦略を見事に体現しています。
産学連携における「翻訳」の重要性
ここまで成功の要因を述べてきましたが、産学連携は単に学生にアイデアを出させれば成功するというものではありません。
このプロジェクトの裏には、学生の尖ったアイデアをビジネスとして成立させるための、企業側の「理解」と「翻訳」があったはずです。
「遊び」を「ロイヤリティ戦略」へ
学生が提案した「キャラ育成ゲーム」というアイデアを、企業側は「顧客ロイヤリティを高めるためのCRM(顧客関係管理)戦略」として解釈し直す必要があります。
- 学生:「キャラが育ったら楽しいじゃん!」
- 企業:「それは来店頻度の向上(LTV向上)に繋がる施策だ」
このように、学生の感性(右脳的アプローチ)を、ビジネスの論理(左脳的アプローチ)に落とし込み、社内の決裁を通す。この「翻訳力」を持つ担当者がいたからこそ、突飛とも思えるアイデアが実装に至ったのでしょう。
また、学生にとっても、自分のアイデアが実際のアプリとして実装され、全国のユーザーに使われる経験は、大学の授業だけでは得られない貴重な学びとなります。企業と大学、双方がWin-Winの関係を築けた好例です。
まとめ:自社のビジネスに「異分子」を取り入れよう
未来屋書店と女子美術大学の事例から学べることは、以下の3点に集約されます。
- 「作業」を「エンタメ」に変える: 面倒なプロセス(アプリ提示など)にゲーミフィケーションを取り入れ、能動的なアクションに変える。
- 「世代間のギャップ」を武器にする: 社内の会議では出てこない「若者のリアルな感覚(推し活、ナラティブ)」を、産学連携を通じて取り入れる。
- 「情緒的価値」で差別化する: 機能や価格で勝負できない市場こそ、体験や物語といった「感情の価値」を付加する。
現代のビジネス環境は変化が激しく、過去の成功体験を持つベテラン社員の判断だけでは、最適解を導き出せない場面が増えています。 そんな時、全く異なる価値観を持つ「学生」という異分子をプロジェクトに招き入れることは、組織の硬直化を防ぎ、イノベーションを起こすための強力な一手となります。
「自社の商品は若者に響かない」「デジタルの施策がマンネリ化している」 そんな悩みをお持ちの企業こそ、一度「産学連携」という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。そこには、社内の常識を打ち破る、新しいヒントが隠されているかもしれません。
いかがでしたでしょうか。 この事例のように、貴社の課題に対して「学生の感性」を掛け合わせることで、思いもよらない解決策が見つかるかもしれません。
弊社では、企業の課題と大学の研究室・学生をマッチングさせるサポートを行っております。「まずはどんなことができるか話を聞きたい」という段階でも構いません。ぜひお気軽にご相談ください。